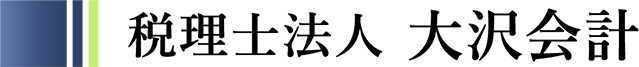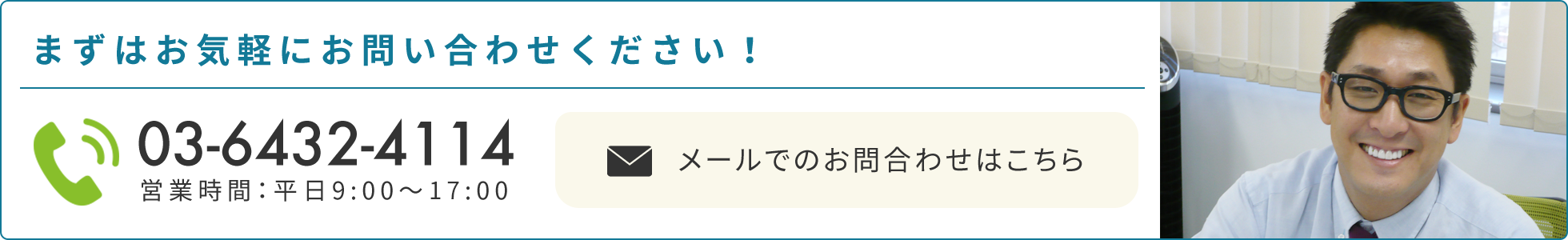2010年8月
H22.8.31
外国人を雇用する際のポイント
経済社会の国際化の進展で、外国人労働者を活用したいという企業ニーズも高まっていますが、2009年の外国人登録者数は、218万人と、増え続けていた登録者数は48年ぶりに減少しました。
外国人を雇用するに当たっては「入管法」や「入管特例法」により、取扱いが定められています。どのような制度があり、また、注意を要する点は何かを見てみます。
在留資格の確認をする
日本国に在留する外国人の方は入国の際に与えられた在留資格の範囲内かつ定められた在留期間に限り就労等が認められています。就労させようとする時は、仕事の内容と期間が在留資格の範囲内であるかの確認が必要です。入管法上の就業が認められる在留資格には27種類ありますが、大きく分けると「活動に基づく在留資格」と「身分又は地位に基づく在留資格に分けられ、「活動に基づく在留資格」の内容は更に3つに分かれています。
外国人登録証明書の確認と注意点
採用に当たっては採用決定前に外国人登録証明書(外国人が90日を超えて日本に滞在する時は入国した日から90日以内に居住している市区町村に届出し登録することになっています。)の提示を求める事は公正採用の面から不適切であるとされていますが、口頭で確認し、採用後に外国人登録証明書を本人から直接提示してもらうのがよいでしょう。又、雇い入れたらハローワークに外国人雇用状況の届出をしなくてはならない事となっています。この届出により氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍を届出します。これは、雇用保険の一般被保険者でない外国人も対象となります。
21年7月に改正された入管法
現在不法滞在している外国人は、11万人と推定されていますが、外国人登録証やパスポート等で在留資格を確認する事が大切です。又、期間についても在留期限や次回申請期間等も確認する必要が有ります。昨年7月に法の一部改正が有り、さらに今年の7月にも施行された改正内容をみると、適正な外国人就労の活用には手続きの円滑化等の緩和策が有り、安全な社会の維持の為、不法な滞在には厳しい措置をとるという方向性が示されたように感じます。
H22.8.30
未知のままの節税潰し
息子に新規の会社を設立させて、親がオーナーの会社の主要な事業と資産を息子の会社に無償で吸収分割させて、親の会社はもぬけの殻にしてしまっても適格組織再編として課税関係が生じず、株主構成を根本的に変える効果を発揮してしまう・・・。
非按分型適格組織再編
しかし、こんな話は聞いたことありませんでした。この行為は無対価組織再編と言われています。無対価組織再編なんていう言葉は聞くだけで難しそうだな、という印象を受けます。でも、大会社のグループ内再編では無対価組織再編は通常のことで、会計基準もあります。
ただし、税法については今年の改正によってはじめて「無対価」という明文の規定創設がされたところです。とはいえ、明文規定の有無に拘わらず、現実に無対価組織再編は行われていたので、現行税法規定で律せられていたところです。
実行には勇気がいるがもう間に合わない
新規定は今年10月1日から適用ですが、9月30日までの法律では、適格会社分割については、分割承継法人の株式以外の資産が交付されないもの、としていました。無対価はこの規定に合致していたのです。組織再編では無対価は適格に含まれる行為で、その結果冒頭の事例のようなスキームが企図され、あり得ないと言われていた非按分型適格組織再編が実質的に可能になってしまっていたと思われます。
目的を以てさりげなく改正
無対価に係る明文規定創設の目的は非按分型組織再編潰しと思われます。改正規定の最も典型的なものは「一の者」という言葉です。これに触れている解説書は今のところ皆無なのですが、この言葉は法律と政令に100回近く出現します。9月30日までの法律では例外なく、個人の場合は「一の者」の後に( )書きをつけて、同一親族グループを意味するものにしていました。それが10月1日以後の法律では、組織再編の場面ではことごとく( )書きのない「一の者」になっています。
知られないままの封じ手
冒頭の事例のような、父親の会社と息子の会社は、新規定では、別々な「一の者」により支配される会社になりました。10月以降は、冒頭の事例は適格要件を欠く組織再編の事例ということになりました。
多くに知られないまま封じられることになった節税策だったのかもしれません。
H22.8.27
離婚の際の財産分与 相続時財産分与との矛盾
離婚時財産分与では取得者非課税
離婚の際の財産分与では、分与を受けて財産を取得する側は非課税です。すでに財産分与請求権があり、その請求債権の弁済として財産を受け入れているだけだから、という理由です。そして、妻のその取得財産の取得費はそのときの時価となります。
逆に、財産分与する側がモノで財産分与したら、時価でそのモノを譲渡したこととして、分与者が課税されます。
相続時財産分与では取得者課税
もし、離婚時の妻に財産分与請求権という債権的財産がすでに確定的に在るのだとしたら、夫の相続時まで添い遂げた妻には当然にそれ以上に強い財産分与請求権という債権的財産があるべきです。
それが妻への「配偶者に対する相続税額の軽減」で表現されているということであるならば、「配偶者に対する相続税額の軽減」の対象となった財産については、その取得費は相続時の時価であるべきです。
離婚の場合との整合性がとれていません。
相続課税との二重課税禁止判決の反射効
二重課税禁止最高裁判決は二重課税の回避として相続税課税済額を所得計算から排除することを要求しています。
この新判例の解釈論理は、年金だけでなく、不動産などの場合にまで二重課税排除を要求していると解するのがスジです。そういうスジ論からすると、相続時財産分与で取得する配偶者税額軽減対象財産については相続税でまず非課税扱いとなり、次いで、これを譲渡するときには相続時課税済みとして、相続税評価額までの金額については重ねて課税されることはなくなります。
これで、相続時財産分与と離婚時財産分与の取扱いが類似し、整合することになりました。最高裁新判例の反射効というべきです。
離婚時と相続時の相違と整合
離婚時財産分与では取得者非課税で分与者課税、相続時財産分与では取得者非課税で分与者課税ナシです。
相続時財産分与では分与者への課税がないので、取得者の取得費は相続時の時価ではなく、分与者の取得費の引継ぎということになります。これはこれで整合的と言えます。
これをまとめると、相続財産の二重課税排除を含めた、配偶者への相続時財産分与後の譲渡所得計算は次のようになります。
(譲渡収入-相続税評価額)-引継取得費×(譲渡収入-相続税評価額)÷譲渡収入=譲渡所得の金額
H22.8.26
離婚の際の財産分与 妻の権利、夫の義務の発生
離婚時財産分与での債権債務
離婚の際の財産分与では、分与を受ける側に財産分与請求権があり、他方に財産分与義務があると言われます。
分与者がモノで財産分与したとしたら、
(借)分与義務××/ (貸)分与財産××
/ (貸)譲渡損益××
分与を受ける側の会計処理は、
(借)取得財産××/ (貸)分与請求権××
と、表現することができます。
それでは、配偶者の財産分与請求権と相手側の財産分与義務はいつどのようにして発生してくるのでしょうか。
債権債務の発生過程
妻に財産分与請求権の発生があり、夫に財産分与義務の発生があったとして、その債権の発生の原因は役務の提供であり、債務の発生の原因は役務の受け入れである、と考えるのが順当です。その役務とは、一般的には「内助の功」というものです。
妻には、内助の功という役務収益が、
(借) 未収債権××/ (貸)役務収益××
夫には、内助の功への支払費用が、
(借) 内助費用××/ (貸)未払債務××
なお、内助の功としての役務収益及び内助費用については、現行所得税法では課税対象外の収益費用です。
債権債務の蓄積の結果
債務の弁済が妻への生活費部分の資金源の提供額を超えて、多額の未払部分の発生となって普段に蓄積され、離婚のときに顕現して、財産分与請求権と財産分与義務とになる、ということでしょう。
ここでの役務収益には課税がないままその対価としての債権の発生が認められています。それに対応するように、内助費用の対価としての債務の発生は認められるものの、費用として課税所得を減殺する効用は配偶者控除・配偶者特別控除にて少し考慮されるだけで、基本的には効用を発揮しないまま消滅しています。
隠れた非課税所得の対価の回収
離婚時に突然、財産分与請求権と財産分与義務が発生するのではないとしたら、上記のような発生過程があるはずです。
その上で、妻には経常的非課税所得があり、夫には無視される内助費用が形状的に発生している、というふうに考えれば、離婚時の税務関係は理解しやすくなります。
H22.8.25
離婚の際の財産分与 何故あげる側に課税なのか
離婚の財産分与では分与側に課税
離婚の際の財産分与では、分与を受けた側には贈与税も所得税もかかりません。
それに対して、分与した側が居住不動産や有価証券などで分与義務を履行すると譲渡所得税の対象となります。
この理屈は、世間の常識とは相当に異なります。分与側に税金がかかるなら、その財産分与契約には重大な錯誤があったので無効、という主張で裁判を起し、結果的に課税処分の取消しも獲得した、という事例もあります。
分与側に課税する理屈
財産分与と離婚慰謝料と併せて5000万円の支払いをするとして、これに充てるため取得費2000万円の不動産を5000万円で売却して支払った人と、その不動産を金銭支払いに替えて離婚相手に引き渡した人とは、同じ課税関係になければ衡平ではありません。
不動産の他人への売却には、確定申告での譲渡所得の申告が必要で、ここで課税されます。また、法解釈上財産分与は譲渡行為に含まれており、財産分与だからと言う理由での特別な配慮規定はありません。
財産分与義務という債務の弁済のために金銭ではなく、モノによる代物弁済をしたという理解が課税の理屈です。
分与を受ける側の非課税の理屈
婚姻中の夫婦は共同して財産形成をしているので、財産が一方だけの名義の場合には、もう一方には、共有財産としての顕在的な持分は認められないものの、潜在的な持分があり、財産分与の場合にそれを清算する請求権として顕在化することになる、と解されています。
従って、財産分与請求権という債権の弁済として離婚相手から金銭や不動産その他の財産を受け取る、ということなので、無償の贈与にはなりません。
分与側の課税への注意点
自宅を売却した場合には3000万円の特別控除や軽減税率の適用がありますが、これは夫婦や直系血族等の間での取引では適用できません。
したがって、離婚のための準備行為として早々に財産分与による名義変更をおこなったような場合には、特別控除が使えない場合が起こり得ます。要注意です。
H22.8.24
マイナスの利積資積と清算所得廃止
利益積立金とは
現在の税法では利益積立金とは「法人の所得で留保している金額をいう」とされ、過去の累積留保利益を意味するもので、委細の政令委任により、〇〇〇に掲げる金額の合計額から〇〇〇に掲げる金額の合計額を減算した金額、と規定してマイナスの数字もあり得る、との表現になっています。
平成12年までは、〇〇〇に掲げる金額が〇〇〇に掲げる金額を超える場合の超える部分の金額、との表現によりマイナス金額はあり得ないことを示していました。
清算所得課税はどうなる
マイナスの利益積立金というのは、過去の累積の欠損金を意味します。
残余財産-資本金等-利益積立金=清算所得
清算所得課税の公式はこの通りなのですが、大赤字つづきの会社が清算すると、マイナスの利益積立金についてマイナス計算することになり、課税所得が生ずることになってしまいます。これは不合理なことなので、実務においては、マイナスの利益積立金は清算所得計算上ゼロと扱っていました。
法律の奇怪な改正によりあまりに不合理な事象を生ぜさせておいて、実務では法律を無視して課税の留保をすることは、法治国家ではあるべきではありません。
恣意的な運用に至る
事前に国税局(税務相談室)に対し電話確認で「解散時の利益積立金額がマイナスの場合は0円として取り扱っている。」との回答を得ているにもかかわらず、税務調査において、利益積立金がマイナスの場合にはマイナスのまま計算すべきである、という理由で更正処分を受けたという事例があります。清算中に含み益のある資産の譲渡が行われていたのが理由ですが、マイナスをゼロとするのも法律無視ながら、別なケースではマイナスの全部または一部をマイナスのマイナス処理するのも恣意的です。
徴税権力の恣意性を排除することに租税法律主義の立法精神があるはずなのに。
清算所得課税廃止の誘因か?
この事案は、国税不服審判所で納税者敗訴となっています。資本金等でも、MBOの結果の自己株取得で多額のマイナス資本金等を生じさせているケースでは同じ不合理計算になります。
今年の清算所得廃止の改正は、平成13年の奇怪立法のツケをここで解消しようという誘因で企図されたようにも思われます。
H22.8.23
定年後再雇用時の社会保険の手続き
再雇用されて継続雇用する時は
会社で定年を迎えても同一の事業所で引き続き再雇用されるケースが増えています。
高年齢者雇用安定法の改正で平成18年4月から平成25年までの間に65歳未満の希望者に対して「雇用確保措置」を講ずることとされており、①65歳までの定年の引き上げ、②継続雇用制度の導入、③定年制の廃止、の3種類の中からどれかを行う必要があります。又、年金が満額支給となるのは、今年60歳を迎える昭和25年生まれの人で満65歳ということもあり、定年前と勤務条件は変わっても継続して働くことが多くなってきたようです。
社会保険の同日得喪の特例
定年により退職した65歳までの人が1日の空白もなく同一事業所で引き続き勤務する場合、再雇用に伴う給与の変動(普通は降給)と在職老齢年金の調整額を即応させるため、被保険者の取得と喪失を同時に行う「同日得喪」の特例が適用されます。
対象者は次の条件を満たす場合
①定年退職で引き続き再雇用される場合
②特別支給の老齢年金の受給権者(未請求者を含む)である場合
手続きは定年退職日の翌日に「被保険者資格取得届」と「被保険者資格喪失届」を提出するとともに定年時を確認できる就業規則の写し、退職辞令の写、事業主の証明等のいずれかを添付して提出します。
同日得喪の届出により退職日の翌月から新しい標準報酬の保険料となります。これにより、本人と事業主の保険料負担が早期に軽減されます。定年時の得喪でなく、別の時期に賃金改定を行った場合は通常の月額変更届となり変更後3カ月経過後の4ヶ月目より改定となります。又、在職老齢年金は同日得喪を提出することにより定年時までの厚生年金加入期間で計算され、年金の支給調整額は再雇用後の新給与額に基づいた新総報酬月額相当額で計算されます。
H22.8.20
最高裁二重課税判決の波及効果
二重課税禁止最高裁判決の計算構造
先月7月6日の年金二重課税禁止最高裁判決の新判例は、二重課税の回避として相続税課税済額を所得計算から排除することを要求しています。また、所得税法は支払済保険料を所得計算上控除するものとしています。これをまとめると次の計算式になります。
(年金収入-相続税評価額)-年金対応支払保険料按分額=年金所得
算式の相続税評価額は相続時評価された年金受給権のうち、その年の年金収入に対応するように計算したあとのものです。
控除する支払保険料については、まず過去の累積支払保険料総額を毎年の各年金に収入比例的に対応計算させることになっています。その対応支払保険料はさらに、その年の年金収入全体にかかわっているので、課税済み部分と未済部分とに按分計算し、未済部分に係るもののみをその年の年金収入から控除する支払保険料にするものと考えられます。
年金以外の資産の場合
年金以外の資産でも、計算構造は基本的に変わらないはずです。むしろ、相続税の課税を受けた資産を何回かに分けて分割収受するようなものは少ないでしょうから、計算はより単純です。
不動産の場合は相続税評価額が物件ごとに算出されていますので、課税済分と未済分とに過去の取得費及び譲渡費用を按分計算するだけです。株式等有価証券の場合も基本的に同じです。
過去に100万円で買った土地を600万円で相続時評価され、1000万円で売却した場合、
(10,000,000-6,000,000)-1,000,000×4,000,000÷10,000,000=3,600,000(譲渡所得の金額)
という計算になります。
年金以外に触れようとしない
年金の事例も過去何十万件かあるようで、後処理が大変でしょうが、件数で言えば株式等有価証券になるとさらに想像を絶する件数になるでしょうし、不動産の譲渡所得のことになるとこちらは金額的に想像を絶することになると思われます。
こういう理由からなのでしょうが、当局も、多くの識者も、マスコミも最高裁の二重課税禁止判決効果が株式等有価証券や不動産などにまで及んでいることに触れようとしません。
また誰かが二重課税確認裁判でもしないとダメなのでしょうか。
H22.8.19
111歳事件と相続申告
即身成仏と即身仏
30数年前、「即身成仏する」と自室に閉じこもり、水や食事を絶って、そのままミイラになった、というニュースは衝撃をもって配信されました。現代社会の家族関係を表象するような社会病理現象と受け止められたからだと思います。
正確には、「即身成仏」とは、仏教で人間が生身のままで究極の悟りを開き、仏になることで、それに対して、修行者が瞑想を続けて絶命し、そのままミイラになることは「即身仏」と言われるそうです。
相続税の申告はどうなる
即身仏が億万長者だったら、相続税の申告義務はどうなってしまうのだろうか、などと、職業柄ついつい考えてしまいました。
民法では、「相続は、死亡によって開始する」と定めていますので、30数年前に「即身仏」になったところで相続は開始されていることになります。
無申告に対する税務署長の税額決定権限行使は法定申告期限から5年以内に限定されており、それとともに、法定納期限から5年で納税者の納税義務も時効により消滅するとされています。
即身仏となった億万長者の相続税は徴収不能なのでしょうか。
法定申告期限がポイント
相続税の申告書の提出義務の法定申告期限は、その相続の開始があったことを知った日から10ヶ月です。すでに即身仏になっている父親の死亡に、相続人が気付かなければ、たとえ30数年経っていても、法定申告期限や法定納期限の計算そのものが始まりません。「相続の開始日」ではなく、その開始を「知った日」から申告期限の期限計算が始まるからです。ただし、たとえ30数年後でも、申告義務を法定申告期限内に果たせばペナルティーはありません。
それでも法の想定外
とは言え、30数年前の法律に基づき、30数年前の相続財産を確定し、それをその当時の評価方法で評価し、申告納付するということには、法の想定外な不都合が多々生じそうです。
引継ぎ資産にかかる所得税の申告については、「知った日」以降に相続人に申告義務が移るのではありません。即身仏には当初から申告義務がなく、申告がなされていたら、それは無効申告であり、かわりに相続人に申告義務があることになり、30数年間の申告義務の無履行ということになります。
H22.8.18
仕事のゲーム化
野球やサッカーのゲームはテレビ観戦でも面白いし、競技場へ足を運んでプロの試合を実際に観戦するともっと楽しめ、さらに自分でゲームに参加したらもっと面白い、と言うように、リアルになるほど、自分の身体感覚を駆使するほど自ら創意工夫して相手と競争し合い、勝敗を決する楽しさや五感の興奮度が高まります。
“仕事のゲーム化”のすすめ
“ゲーム”には人の創造性や健全な競争意識を刺激する性質がありますから、その性質を社員の主体的・創造的な仕事への取り組みに活用することは、やり方次第で高度なマネジメント施策になります。
それは決して「単純に楽しければ良い」のではなく、人間の集団である組織が、「明るく、楽しく、真剣にチームワークで業績向上」を目指し、創意・工夫を凝らしながら健全な社内競争を繰り広げるものでなければなりません。
そこには、良く考えられた組織活性化戦略・人材育成戦略が組み込まれ、社員の業績向上への挑戦意欲・目標達成やプロセス
スの創意工夫・苦心を通じた自己成長・自己実現の喜びが生まれ、結果として業績改善に結びつくような仕組みづくりと運用を行うことが大切で、次のような一般的方法と留意点があります。
ゲーム化の方法と留意点
1. ゲームの参加者・チームを構成する。
2. エキサイティングな得点ルール・評価表彰基準・公正感のある評価者を決めて公表するなど雰囲気づくりをして期待感を高める。
3. キックオフセレモニーをやり、チェアマンの社長が、ゲームの趣旨と評価ポイント・運営方針・表彰内容を発表するとともに、チームリーダーに「勝利宣言」をしてもらうなど盛り上げる。
4. 仕事ゲームの中で、各チームが失敗を自ら反省して改善し、新しい発見や創意工夫を行い、積極的にトライアルして効果を確かめるように奨励する。
5. 前期リーグ・後期リーグ・年間優勝など
各チームが自ら作戦を立てて、チャレンジするなどプロセスと結果を楽しむ。
このような“仕事のゲーム化”が業績向上と同時に体験による人材育成になります。
H22.8.17
最高裁二重課税判決の計算
最高裁二重課税禁止判決の所得計算
年金への所得税と相続税の二重課税を禁ずる先月7月6日の納税者逆転勝訴最高裁判決の年金所得の計算は、次の通りです。
年金収入-相続税評価額=年金所得
また、被相続人の死亡日を支給日とする第1回目の年金の相続税評価額は死亡時の現在価値と一致するはずだから支給額と同額、としています。従って、年金所得はゼロです。2回目以降のことについては触れていません。
2回目以降の計算はどうなる
本件の年金は230万円で10年間に亘り受け取れるものです。相続税評価額は年金総額2300万円の6割の1380万円で、この年金のための過去の支払済保険料総額は721,977円でした。
2回目以降に控除できる相続税評価額の総額は、1380万円-230万円=1150万円で、これを2回目から10回目までに配分することになります。配分額は逓減的になるはずですが、それを表現する簡単な算式はあるでしょうか。
複利現価法で計算すると
この事例に適合する複利割引率を計算すると年13.704463%となり、これによる第2回目の控除額は2,022,787円第3回目1,778,987円第4回目1,564,571円第5回目1,375,997円、第10回目は723,986円です。
これまでの計算方法はどうだった
従来は、支払保険料の総額に、その年の年金を掛け、年金総額で割ったものを控除する必要経費としていました。
本件の場合では収入が毎年同額なので必要経費も毎年同額になります。
年金収入-年金対応支払保険料=年金所得
また、年金収入から控除する支払保険料には、被相続人の支払保険料も含まれると解されております。
支払保険料の控除方法のあり方
支払保険料の総額を年金収入から差し引くのは所得税法の定めなので、最高裁判例によっても変更はありません。
最高裁の新判例は、必要経費として相続税評価額を控除しているのではなく、二重課税の排除として収入から相続税評価額を除外していると考えるべきです。よって、控除する支払保険料は、相続税評価額部分とそれを超過する部分ごとに按分して差引計算するのが順当です。
なお、本件判決での生保年金収入は全額二重課税部分なので、控除保険料も按分不要で、課税計算外となりますが、判決はこのことには触れていません。
H22.8.16
業務委託契約もいろいろ
業務委託を定めた法律上の規定はない?
業務委託契約とは、依頼主の業務の一部または全部を委託先に任せる際に締結する契約をいいます。従来から事業者間の取引で広く結ばれる契約であり、聞いたことがない方はいないでしょう。
しかし、実は業務委託契約の中身を定めた法律上の規定はありません。民法は、典型的な契約として13種類の契約(典型契約といいます)を定めておりますが、業務委託契約という類型はありません。
そのため、「業務委託契約だから法律上こうなる」というのではなく、当該契約の趣旨や中身に照らして、そもそもいかなる内容の契約なのかがまず問題とされます。実際には、民法上の請負契約、委任契約、それらに近いもの、あるいは、両者が混合されたもの等といろいろです。
請負と委任
因みに、請負契約は請負人がある仕事を完成することを約し、注文者がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを内容とする契約です。これに対し、委任契約は、ある事務の処理を自分以外の他人に任せる内容の契約をいいます。
請負契約はその目的が結果、成果物の完成に向けられているのに対し、委任契約の目的は委任する事務の遂行そのものにあります。その違いは報酬の支払われ方、トラブルがあったときの契約不履行の成否等に微妙な影響を与えます。
そこで、具体的トラブルの処理では、契約書上の文言は勿論のこと、契約の趣旨に照らして、民法上手かがりとなる規定を探し出し、当てはめるということになります。
雇用の代替手段として用いる場合
ところで、近時、人件費の削減、雇用に伴う解雇などのリスクの回避を目的として業務委託とする例があります。しかしながら、両者の間に使用従属性が認められる場合には、労働基準法上の労働者として、同法による規制を受けることがあることに留意が必要です。
例えば、業務の遂行について裁量がない、報酬が時間や日数で算出される、従業員と同様の業務をしている、給与所得として源泉徴収票を出している、労働保険を適用させている等の要素がある場合には、労働者性が認められる可能性が高くなります。
H22.8.6
就業規則・賃金規定の見直しで保険料削減
景気に明るさが見えてきたとは言え、中小企業の景気回復はもう少し先になりそうです。このような中、今一度会社の経費削減の一つ社会保険料の削減について考えてみましよう。これまでも削減策はありましたが、一歩進めて、就業規則や賃金制度の見直しで削減の方法を探ってみます。
会社のルールを見直す
会社では入社から退職までの勤務中の決まり事を就業規則で規定しますが、それを少し工夫して節減する事が可能となります。
①退職日の決め方
社員が月末退職するとその月の保険料がかかります。例えば定年退職日を「定年を迎えた月の月末とすると定めている場合は、その会社が月末以外の賃金締切日であるなら、賃金締切日を退職日とすればその月の保険料はかからない事となります。
②通勤費の支給方法
社会保険料の標準報酬月額を決める時は、
通勤交通費が含まれます。毎月1カ月分を支給している場合は、6カ月定期に切り替えると通勤費も下がり、社会保険料の等級を下げられるケースもあります。
③年収の高い人は年俸制も検討
幹部社員等でおおよそ年収800万円以上の人は厚生年金保険料の上限月額62万円×12カ月以上の額となりますので、賞与を支払っているなら年俸制の方が保険料は安くなります。但し、賞与は業績により上下するものですが、年俸制では固定的賃金となるので、注意が必要です。
④昇給月を7月にする
毎年算定基礎届により、4月から6月までの賃金額を平均し、その年の9月からの保険料額を決定しますので標準報酬の等級差が1等級にしかならない小幅の昇給の場合は昇給月を7月にすると、翌年の9月の定時決定まで改定が先送りとなります。
但、7月から9月の間に残業等が多い時に2等級以上の差となる時は10月月変となります。この方法は降給の時は逆に高いまま継続されるので、注意が必要です。
⑤給与改定は標準報酬月額表を考慮する
通勤費を支給していない場合は、賃金表を改定する際、標準報酬の月額表を意識して給与額が表の等級のどこに位置するかを考えて給与額を決定するのも一つの方法です。
H22.8.5
エコ減税とエコポイントを試してみよう!
目標達成・課題解決のために、ビジネスでは「企画」と言う思考技術が不可欠です。
企画業務は、企業が持てる専門技術や知識をビジネスのカタチにするもので、商品企画・研究企画・販売企画等で担当者やチームが様々な思考・創意・工夫を行っており、その優劣やスピードが競争力の源泉となる重要性をもっています。
システム思考とは
今世紀の初め、動植物の社会を研究の焦点にしていた生態学者たちが、クモの巣のように拡がる関係のネットワーク・ 生命網というべきものを観察し、そこで見つけた新しい思考法が、事物をそのつながり・結びつき・関係から考える方法、つまり システム思考 です。
システム思考の最大の特徴は、企画内容を「部分の集合」ではなく「部分と部分の相互関係・全体として一体的な構造的関係」が生まれるように、思考プロセスをたどる点にあります。
「システム思考」は唯一絶対的な思考法が存在する訳ではなく、課題によって様々な工夫がされていますが、例えば「役に立つ企画の立て方」でご紹介した「目的設定、・現状把握・SWOT分析・目標設定・成功要因獲得とハードル解除策検討・スケジューリング」の一連の思考順序はシステム思考になっています。
システム思考のメリットと留意点
システム思考で企画すると実務では次のメリットが生まれます。
①目標達成・課題解決へ向けた思考が論理的・実務的に考え易い。
②思考プロセスでの迷い・停滞・抜けや判断の誤りによる手戻り等の無駄が避けられ、効率的に企画業務が遂行できる。
③上司や関係部門との議論の的が絞りやすく、合意形成が早い。
④企画業務の現場で便利に使われ、定着し易い。
⑤企画を実現する推進過程で、予期せざる障害に出会っても、原点に戻ったり、プロセス修正するなどの対処がし易い。
基本的留意点は次の2点です。
①“三現主義”に立った的確な状況判断に基づいて思考すること
②一貫して創造的発想で目標・達成具体策などを考えること
H22.8.4
禁煙治療費も医療費控除!
タバコ税の増税は10月1日から
2010年度税制改正でたばこ税の増税が決まりました。1本あたり3.5円(国・地方それぞれ1.75円)が引き上げられ、1箱あたり100円程度値上がりする予定です。増税は今年10月1日からの適用となります。
禁煙治療も医療費控除の対象に
昨今の喫煙環境が厳しくなっていることに加え、このたばこ税の増税を受け、最近愛煙家の間で「禁煙治療」への関心が高まっているようです。
禁煙治療とは、医師の指導のもとでニコチン依存症を改善し、禁煙を実行していくものです。以前は保険の対象外でしたが、2006年4月から医療診療報酬の改定により、禁煙治療についても医療保険が適用されることとなりました。
そこで、タバコ税の増税を機に禁煙に挑戦している方に朗報です。禁煙治療にかかった費用も医療費控除の対象になります。ただし、医療費控除を受けるためには、医療費として認められるものでなければなりません。
医療費として認められるものとは
所得税法施行令では、医療費控除の対象となるものは主に
1 医師又は歯科医師による診療又は治療
であること。
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入であること。
としか規定していません。解釈すると以下のようになります。
既に病気になっており、その治療の一環として禁煙治療を受ける人はもちろん、病気でなくても、医師の指導により禁煙治療を受けたのであればその禁煙治療費は医療費控除の対象になり、また、医者から処方箋をもらって、ニコチンガムなどの禁煙補助薬を購入した場合は、医療費控除を受けることができます。
H22.8.3
最高裁二重課税判決の意義
最高裁二重課税禁止判決の独自内容
年金への所得税と相続税の二重課税を禁ずる先月7月6日の納税者逆転勝訴最高裁判決(長崎地裁は勝訴、福岡高裁は敗訴)の内容は、勝訴していた長崎地裁の判決と少し異なります。
地裁は、年金への課税は相続税で済んでいるのだから、所得税で再課税すべきではない、としたのに対し、最高裁は、相続税の課税済み部分はその後の所得税課税において重ねて課税してはならない、です。
年金についての二つの非課税
所得税法には元々退職遺族年金非課税の規定がありました。今回の年金判決で争点だった「相続取得によるものは非課税」との規定により、退職遺族年金以外の遺族の受け取る年金も、非課税が確認されました。
それでは、元々の退職遺族年金非課税規定は特別に法律規定がなくてもよかったことになったのでしょうか。この疑問は、被告の国税サイドが反論として何度も主張していたところでした。
最高裁判決の独自内容の意味
相続税が課税される相続財産の価額と、所得税が課税される所得の収入金額とには一時の一括課税か、何回かの分割課税か、長期間経過後の課税か、という理由による相違があります。その相違からくる金額差の部分にのみ所得税は課し得る、というのが、最高裁判決の独自内容です。
その独自内容によって、先の、二つの年金非課税の疑問に答えたのです。即ち、退職遺族年金は相続課税と無関係に非課税、相続取得年金は相続課税部分のみ非課税、という理解です。
新たな考え方による法解釈
最高裁判決の独自内容の意義は、相続税は一種の特別な所得税なのだから、相続税の課税済み分部にその後の所得税課税が重複してはならない、と言うことです。
年金について言えば、従来は、過去に支払い済みの保険料(被相続人が支払ったものを含む)を超過して受け取る年金部分が所得税の課税対象と理解されていました。
今度は、この支払原価超過分への課税の前に、相続課税済部分を除外する、と大きく課税対象に変更を加えたのです。
そして、この新たな考え方の影響は遺族年金への課税問題にとどまらず、相続財産に関わるその後の所得税課税全体に及ぶことになります。
H22.8.2
最高裁「二重課税」判決の射程
年金に相続税と所得税を二重課税するのは所得税法違反、と国側敗訴にする最高裁判決が7月6日に下されました。
二重課税の意味
相続による財産の取得は、所得税法における「所得」であるが、課税は相続税法に委ねているので、所得税法では非課税と定めています。
この非課税規定は、税法の重要な原理規定なのですが、その原理を再確認したのが今次の判決です。
相続税法での課税の特徴
相続税の課税対象には、所得税では課税されない未実現の所得も取り込まれます。将来取得年金の予定額が課税対象となったのはそのためです。類似のものとしては、
①預貯金・貸付金の未収利息等
②3ケ月以内収穫予定の天然果実
③訴訟中の損害賠償金などの債権
④生命保険契約に関する権利
その他があります。
これらが、実現所得となったときには、相続税での評価額部分を超える額だけが課税されるべきです。源泉分離の利子課税などは、二重課税排除を確定申告による源泉税の還付で行うとなると、そうできるようにするための法改正が必要です。
二重課税を定める矛盾規定
さらに、もっと重要なことは、相続取得財産については相続税で時価課税して、また、その時価で所得税を二重課税するものが沢山あるということです。
それは、不動産や株式などの譲渡性資産です。相続財産を譲渡するときに、相続税課税済みの金額部分に再度課税します。明らかに二重課税です。
これらの法律内部の矛盾規定は、この二重課税禁止判決を承けて、見直されるべき事態に至ったと言うべきでしょう。
アメリカの相続・贈与税・譲渡税
アメリカの相続税は遺産課税で贈与税は贈与者課税なので、相続財産は死亡時に被相続人が相続人に譲渡したような扱いになり、相続人が取得する相続財産に付せられる取得価額は相続時の時価となり、二重課税は排除されるようになっています。
民主党は政権政策で遺産課税を唱えていましたので、近い将来に米国と同じ制度にするつもりなのか、関心の湧くところです。