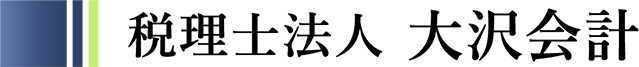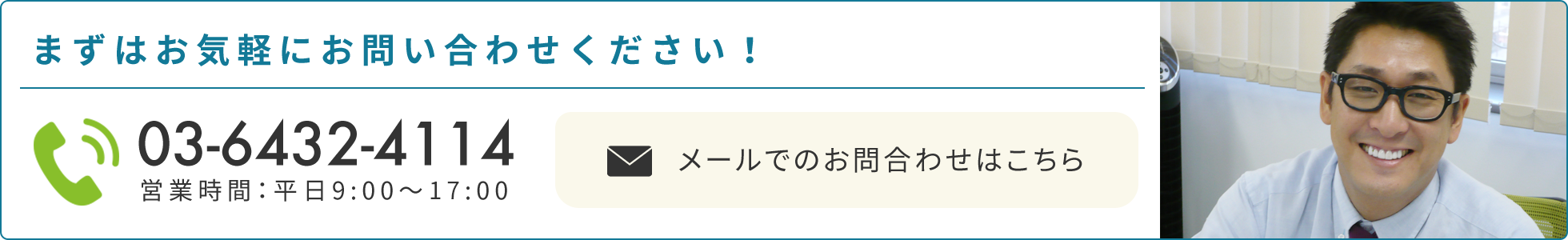2011年1月
H23.1.31
手続的民主主義が光っている
功績倍率法が普遍的
役員退職金について、法人税法では「不相当に高額」な部分を損金不算入としています。いわゆる過大役員退職金問題です。
役員退職金をいくらにすればよいかの話題のときの適正額の限度基準としては一般に功績倍率法が多く採用されています。
功績倍率法は、「役員の最終月額給与×勤続年数×功績倍率」の算式で表現されます。
功績倍率の無難値
この算式の中で、最も争いの種になるのが「功績倍率」の部分ですが、代表取締役社長の退任については一般に「3」を採用すれば無難と解されています。
「3」を無難とする法律や通達の根拠はないのですが、判決の積み重ねの中で基準値として確立してきたものと言えます。
モデル判決
最も基準とされる判決は昭和55年5月26日の東京地裁判決です。この訴訟で被告税務署長は「全上場1603社の実態調査の結果から算出される功績倍率の平均が社長3.0、専務2.4、常務2.2、平取締役1.8、監査役1.6」であると主張し、これが高裁、最高裁の判決においても採用されて、以後の税務行政に影響を与えてきました。
それでも異なる個別事案判決
とは言え、その後の判決の中でも、昭和63年9月30日の静岡地裁判決は功績倍率2.2を採用し、平成19年11月15日の国税不服審判所の裁決では1.9を採用していますので、功績倍率3.0が必ずしも安全値と言えるわけではありません。
逆に、昭和51年5月26日の東京地裁判決では7.5、最近でも平成16年6月15日の国税不服審判所の裁決では4.7を採用するなどのケースもあります。
スジ論と形式論
本来、役員退職金をいくら支払うかは、会社が主体的に判断することで、他に基準を求める話ではないともいえ、会社への貢献の度合いを分析的に明らかにし、資料的に整えることを通じて、算定することが重要です。
そうではあるものの、事前に功績倍率法の各算定項目事項を整備し、功績倍率「3」を採用しておくことが、役員退職金の金額妥当性の税務調査時の説明上、有効性を確かに持っているように感じられる所です。
H23.1.28
銀行救済の為には異常立法も
欠損金の繰越控除とは
赤字(欠損金)が出たら、翌期以降の黒字(課税所得)と相殺できる税務上のルールがあります。これを欠損金の繰越控除といいます。
繰越の期間は、日本は世界的に最も短く、以前は5年間とされていました。
銀行救済のための欠損金税制改正
7年前、金融庁は税制改正要望として、銀行破綻を救うために、銀行については赤字の繰り越しの期間を5年から10年に延長することを求めました。その結果、平成16年度の税制改正では、欠損金の繰越控除期間が5年から7年に延長され、さらに大幅な損失を計上していた過去3年前に適用期間を遡及することになり、要望の10年が実現しています。総予算枠70兆円と言われた公的資金の投入で銀行救済もされていたので、さすがに銀行のみの優遇措置とするのははばかられてか、制度は全ての企業を対象とすることになりました。
銀行の法人税の納付状況
公的資金投入後、大手銀行は順調に業績を回復していたところ、平成21年3月期決算では、世界的な金融危機の影響を受け、多くが再び赤字転落しました。ただし、平成22年3月期の決算では、赤字から急回復し、全大手銀行が黒字に再転換しました。
とはいえ、三大メガバンクグループ傘下の6銀行についてみると、過年度の繰越欠損金があった為にここ10数年に亘り法人税をまったく払っていません。
過去、東京都が、業を煮やして銀行課税を企図したものの、敗訴になり、徴税額に対しては巨額の利子を付して返却させられたということもありました。
今後の見通し
そうは言うものの、大手銀行グループの今期の決算見通しは、平成18年、19年3月期の過去最高水準近くになろうという勢いで、一斉にというわけには行かないでしょうが、今後何年かのうちには、一つ一つと法人税の納付が再開されることになりそうです。
そういうことを踏まえてか、税制改正大綱では一転して、繰越欠損金の控除額を8割に制限する(大企業限定)としています。銀行には優しくする必要が終わったあとで、8割を5割に、そして中小企業にもと、枠が拡がることのないように、監視していく必要があるように思われます。
H23.1.27
相続税パニックの足音
相続税課税割合の推移
平成21年中に死亡した人は114万人、このうち相続税の課税対象となった人数は4万8千人、課税割合は4.06%でした。20年は4.2%で、平成13年に5%をきって以後引き続いて4%台の課税割合が続いており、いよいよ平成22年は3%台に突入か、という状況にあります。
近年で、最も高い課税割合を記録したのは昭和62年の7.9%です。バブルの昂進期で、58年に5.3%だったのに、年々うなぎ上りに相続税の課税対象者が増えたわけです。これはマズイッとばかりに当局はそれまで長期に亘り<2000万円+400万円×相続人数>としていた相続税の基礎控除を昭和63年に一気に2倍にしました。その結果課税割合は4.6%に落ちたものの、すぐまたうなぎ上りに上昇し、平成3年に6.8%になったところで再度基礎控除を現在の金額まで上げました。その後は、その効果とともにバブルの崩壊もあって課税割合は減少の傾向をつづけてきました。
適正課税割合は5%?
基礎控除の額を変更してきた過程をみると、7.9%はもちろん、6.8%も多すぎる割合と当局は判断していたことになります。
今次の税制改正大綱では昨年の4.2%をみて、課税割合が少なすぎるとして基礎控除の減額を提案しています。
6.8%と4.2%の真ん中は5.5%です。過去の推移をみて、4.5%~5.5%あたりが適正割合なのかと、推測できそうです。
<3000万円+600万円×相続人数>の効果
これは税制改正大綱で提案されている相続税の基礎控除です。相続人3人の場合、現行よりも3200万円低くなります。
また、死亡保険金一人当たり500万円非課税枠が未成年者・障害者・生計同一者のみの適用と限定され、さらに、昨年改正の非同居実家相続での小規模宅地8割評価減不適用もあり、これで通常5000万円以上の影響があるので、首都圏では相続税の課税対象割合が一気に増えそうです。
相続税の課税対象者のうち、相続財産2億円以下の層が7割を占めており、この層の下にその何倍かの相続課税対象の予備軍がいるわけですから、パニックになるかもしれません。不動産市場へも大きな影響を与えそうです。
H23.1.26
法人成りメリットは縮小か?
法人成りによる節税効果
事業所得者が法人成りする動機に、稼得利益を自分自身への役員給与にし、給与所得控除という架空経費を使う節税効果期待がありました。
それが、今次の税制改正大綱で、役員給与への給与所得控除の圧縮措置がとられたことにより、法人成りの節税効果が減じてしまうことになる、印象があります。
法人・個人事業・役員給与の税負担
次は、法人・個人事業・役員給与の国税、住民税、事業税の合計額の比較です。
収入所得 法人所得 事業所得 給与収入
1000万円 2,271,800 1,941,900 1,121,900
1500万円 3,865,700 3,893,200 2,514,200
2500万円 7,053,700 8,917,500 7,212,500
所得が高くなるに連れて、個人事業の場合の税負担が急速に高くなり、給与所得の場合も法人課税より重くなります。
個人事業での所得が高くなった場合には法人化して、法人所得をゼロにする程度の給与所得を得る、というのが小規模企業での類型的決算行動だったと思われますが、その算段が狂うようになってしまいました。
税負担の変動に対応するには
次は、ある段階での所得や給与収入の100万円増える毎の税額の増加額です。
収入所得 法人所得 事業所得 給与収入
500万円 224,900 193,600 79,800
1000万円 316,700 317,600 237,600
1500万円 318,700 455,900 335,400
明らかに、1000万円前後のところで法人所得と事業所得との、1500万円前後のところで法人所得と給与収入との限界税額の増加の逆転が起きています。この逆転ポイントは以前からあったのではありますが、今次の税制改正大綱では、事業所得で約500万円、給与収入で約1000万円前倒しになることになりました。
税負担の変動に対応するには
すなわち、1000万円を超える事業所得については、給与所得をゼロにしたとしても法人化したほうが有利であり、1500万円を超えるところでは、給与を増やして法人所得をゼロにしてしまうことはかえって不利であることを示しています。
つまりは、一人当り役員給与は1500万円を目安にして頭打ちとし、法人所得は増えるに任せて法人課税にしておく方が全体の税負担の軽減になる、ということです。
所得税と法人税だけで見る限り法人成り節税効果は逆に大きくなっているのです。
H23.1.25
金持ち課税をどう見る
23年度の税制改正大綱の見方
個人所得課税に関する23年度の税制改正大綱の特徴は高所得者課税への方向転換と一般に把握されています。格差是正が焦眉の社会問題だから、という型にはまった類推判断からも、なんとなく当たっている印象をもたせる見方となっています。
所得税の金持ち重課の代表項目
高所得者課税項目としては、給与収入1,500万超部分の給与所得控除は認めない、2,000万円超の役員給与者についての給与所得控除額は激変緩和のもと半分にする、勤続5年以下の役員退職金の「2分の1課税」を廃止する、合計所得金額400万円超の人についての成年扶養親族控除の負担調整をしての適用除外、などがあります。
金持ちだけで終わるのか
財政規模71兆円で国債依存が44兆円と相変わらず税収不足はますます深刻化しています。金持ち重課はまだまだ手ぬるいから、もっと徹底的にやれ、という声になってくるのでしょうか。
税収増をどこで確保するのがよいかという課題では、本当は税率の低い多数派の層のところの課税範囲および税率を外さないことが効果的なのですが、その多数派を一括直撃するのは氾濫をもたらしますから絶対に得策ではありません。急がば回れの例えの通り、少し長期に構えて、まずは所得の高い層に対してのみ負担を求める分断策を採るのが定石です。
所得の高低は相対概念
確かに、最高税率のアップ、配偶者控除廃止の検討は見送りなど不徹底の部分はありますが、少数派としての高所得者への分裂課税の成功は、基準の変更で高所得者の範囲を少しずつ拡大する改正の制度化をもたらしますから、不徹底を叫ぶことは、結局は多数派を「高所得者層」にすることになります。高所得層を厳密化すれば、税率構造の細密化に跳ね返ることになります。高所得というのは相対概念ですから、より低い層から見れば、多数派も高所得層に転化するからです。
大衆課税への突破口
23年度の税制改正大綱の路線は、87%を占める給与所得者への課税を中心に所得税の復権と所得再配分機能の回復を果たそうという路線であり、その開始元年です。
これで終わりのわけがないとすれば、金持ち重課は結果として大衆課税への突破口としての施策であるのは必定です。
H23.1.24
平成23年度税制改正 国際課税編
国際課税については、主な改正として、①外国税額控除制度の見直し、②移転価格税制の見直し、③外国子会社合算税制等の円滑な執行を図るための見直し等があります。ここでは、①の外国税額控除制度の見直しについて、その改正内容を確認していきます。
外国税額控除制度は、国際的二重課税を排除するために、外国で納付した外国税額を、国外所得に対して我が国で納付すべき法人税額(控除限度額)の範囲内で控除するものです。
しかしながら、現行の外国税額控除制度は、二重課税となっていない外国税額も控除限度額の余裕額を利用して控除でき、必ずしも適正に機能していない面もあります。また、日本に本店がある法人もほとんど日本で税を負担しない仕組みなどの制度の歪みがあり、これを是正する必要があることから幾つかの改正がなされています。
「高率」な税率の引下げ
外国税額控除の対象外である「高率」な外国租税水準(現行50%超)を我が国の法人実効税率(引下げ後の法人実効税率)と概ね同水準となる35%超までに引下げました。これにより、二重課税が発生していない外国税額を控除対象から除外することで「彼此流用の余地の縮減」を図っています。
非課税国外所得の全額排除
控除限度額の計算の基礎となる国外所得から非課税の国外所得の全額(現行3分の2)を除外するとしました。同様、これにより「彼此流用の縮減」が図られます。但し、2年間は非課税国外所得の「6分の5」を除外とする激減緩和措置を講じています。
国外所得割合90%制限の廃止
控除限度額の計算の基礎となる国外所得の90%制限に係る特例は廃止することとしました。これにより、我が国での最低限の納税確保を図っています。
外国法人税の定義の明確化
複数の税率の中から納税者と税務当局等の合意により税率が決定される外国の税について、最も低い税率を上回る部分は、外国税額控除制度及び内国法人等の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(いわゆる外国子会社合算税制)等の適用上、外国法人税及び外国所得税に該当しないものとしています。
上記の改正は、平成23年4月1日以後に納付する外国法人税及び外国所得税について適用されます。
H23.1.21
民事訴訟にいう「訴訟費用」とは?
「訴訟費用」の意味
民事訴訟では、判決が出る場合には、当事者が請求の内容として争われてきた内容(例・金銭の支払や物の引渡し等)に対する判断に加えて、訴訟費用をどちらが負担するかについて判断が出されます。
ここにいう訴訟費用とは、民事訴訟費用等に関する法律によって範囲が定められており、訴訟を追行するのに必要なすべての費用を含むわけではなく、例えば、弁護士費用は訴訟費用に含まれません。
「訴訟費用」の具体的内容と負担
訴訟費用は、裁判所に納める訴訟費用(例・訴訟提起の手数料、書類の送達にかかる郵便代)と、証人等に支払われるもの(例・日当、鑑定料等)に区分されます。
訴訟費用は、敗訴者が負担するのが原則であり、全部勝訴(敗訴)であれば敗訴者が全額、一部勝訴(敗訴)であれば裁判所の裁量で各当事者の負担割合を決めます。
「訴訟費用」の回収はどうやるのか
もっとも、実際は、申し立てる側(訴訟では原告)が訴訟費用を先に裁判所に納めることになっております。そこで、実際にそれらを回収するには、勝訴判決が確定してから、別途訴訟費用額確定処分を得て、本来負担すべき者に支払わせることになります。しかし、実際には大変な手間がかかります。手順は、①費用計算書及び費用額の証明に必要な書面を裁判所書記官と相手方に提出する、②相手方より①の各書面の内容に対する意見を出させる、③その上で、裁判所が申立人のかけた費用について、訴訟費用の負担の額を定める処分をすることになります。
「訴訟費用」の金額は低い
しかし、訴訟費用の計上は、こまごまとした上に、個々の金額も低いのが現実です。例えば、訴訟提起料(印紙代)は、100万円の請求で1万、300万円の請求で2万、500万円の請求で3万、その他にも、裁判所の出頭による日当が3950円、書面作成料が基本額1通1500円という具合です。これらを漏らさず積み上げて計算することになりますが、訴訟手続が長引くとその分項目も多くなります。
このように手間暇掛けて確定に至ったとしても金額は高くありません。
以上の実態から、そこまでして訴訟費用の回収をしないのが通常です。
H23.1.20
辞表提出を非受理:昨年の10大ニュースから
海保職員の処分を巡って
昨年の10大ニュースのうち大きな話題の一つに尖閣のビデオ映像流出事件がありました。
この事件は守秘義務違反に当たるかどうかが争点でありましたが、職務上知りえた秘密を漏らしたとされるのかどうかについて、検察は映像流出後に複製版が国会各派に提出されていた事や海保職員なら誰でも閲覧できるフォルダーに一時おかれていた事や過去の起訴例等から映像の機密性は高くなかったと判断し、起訴猶予とされました。海上保安庁の内部では厳罰を望む政府とそれに反する多くの世論からの擁護の声に挟まれ、処分決定に苦渋したようです。
辞職届は処分の後受理された
当初、海上保安庁は問題の職員から提出された辞職届を受理しませんでした。この時海上保安庁は懲戒処分を検討しており、辞職届を受理してしまうと退職となり、海上保安庁として懲戒処分ができなくなってしまうからです。(処分しても効力が及ばない。) 懲戒処分は国家公務員の場合、軽い順に、戒告、減給、停職、免職等がありますが、決定した処分は組織の信用を大きく損なわせた影響を重く見て、保安官を停職12カ月としました。その後、本人からの辞表を受理し、依願退職となりました。
企業に例をとってみると
例えばある会社の従業員が会社に大きな損害を被るような行為を陰で意図的に行っていたとします。会社がそれを察知し、本人に問いただそうとしていた矢先に、本人から退職届が出されて受理したとします。会社は、退職届を受理してしまうと、不正に対しての懲戒処分が出来なくなります。
退職金を払わないようにしたくともできなくなってしまいます。(就業規則で退職後の不祥事発覚時の取り決めがあれば、支払いを減らせる場合もあります。)
もちろん、刑事事件として訴え金銭解決をする方法はありますが、会社の懲戒処分は退職後にはできません。
難しい判断ですが、退職届提出が疑わしい場合は受理しない方が良い時もあるでしょう。しかし一般的な自己都合退職はきちんと退職届を提出してもらう方が労使紛争の未然防止の観点からも必要な事でしょう。
H23.1.19
平成23年度税制改正 納税環境整備(国税通則法)
納税環境整備(国税通則法関連)については、納税者の税負担に直結する改正項目ではありませんが、しかし、更正の請求や税務調査手続き等、実務に大きな影響を及ぼすもの少なくありせん。以下、主な改正項目を確認していきます。
納税者権利憲章(以下「憲章」)の策定
先進諸国のほとんどの国では、何らかの形で、一般的には「憲章」として、納税者の権利や義務を明確にしています。わが国においても納税者の立場に立って、①申告・納税をサポートするために提供されるサービス、②税務手続きに係る納税者の権利利益、③納税者・国税庁に求められる役割・行動、④国税庁の使命や税務職員の行動規範等を内容とする「憲章」を策定することとしています。平成24年1月1日公表となっています。
また、現行の「国税通則法」についても、第1条の目的規定を改正し、同法の法律名も改名することとしています。
税務調査手続き
調査手続きの透明性と納税者の予見可能性を高め、調査に当たって納税者の理解と協力を促し、より円滑かつ効果的な調査の実施の観点から、①調査を行う場合は、原則、調査の日時・場所・調査の目的、調査対象となる帳簿書類等に関して文書で事前通知、②調査終了時には、調査の結果等に関して説明し、その内容を簡潔に記載した文章を交付することとし、また、「更正・決定等すべきと認められる場合」及び「更正・決定すべきと認められない場合」についてもその旨を記載した文章又は通知書を交付することとしています。適用は、平成24年1月1日以後の調査等からです。
更正の請求
課税庁に対して減額更正を求める「嘆願」という法定外手続きの実務慣行を解消し、納税者の救済と課税の適正化・制度の簡素化を図る観点から、①更正の請求できる期間を現行1年から5年(贈与税及び移転価格税制に係わる法人税の更正の請求6年、法人税の純損失等の金額に係る更正の請求9年)に延長し、併せて、増額更正を行うことができる期間を5年に延長、②当初申告要件等のある措置について見直し、更正の請求範囲を拡大することとしています。適用は、原則、平成23年4月1日以後に法定申告期限等が到来するものからです。
H23.1.18
平成23年度税制改正 相続税・贈与税編
平成23年度税制改正における資産課税については、相続税は「格差是正」及び「富の再分配機能の回復」の観点から増税、一方、贈与税は次世代への早期財産移転を一層促進させる観点から贈与しやすくなっているのが特徴です。以下、主な改正項目を確認していきます。
相続税の課税ベース及び税率構造の見直し
(1)相続税における基礎控除は、現行では定額部分5,000万円、法定相続人1人当たり1,000万円ですが、改正案ではこれを3,000万円と600万円に引下げています。
なお、配偶者に対する相続税額の軽減措置、すなわち、配偶者が実際に取得した正味遺産額が1億6,000万円か配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかからない制度は存置されています。
(2)死亡保険金の非課税枠の制限
死亡保険金の非課税措置につては、「500万円×次のいずれかに該当する法定相続人の数」とされています。
①未成年者、②障害者、③相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者。
(3)相続税の税率構造の見直し
現行の税率構造6段階を8段階とし最高税率を55%まで引き上げています。1億円以下までは30%と現行と変わりませんが、2億円以下40%、3億円以下45%、6億以下50%、6億円超55%となっています。
贈与税の税率構造等の見直し
(1)暦年課税については、直系卑属(20歳以上)を受贈者とする贈与税の税率構造が緩和されています。贈与財産300万円から4,500万円までについては税率の引下げがあり、贈与しやすくなっています。なお、贈与財産4,500万円超では、最高税率55%と引上げられています。
(2)暦年課税で上記(1)以外の贈与財産に係る贈与税の税率構造については、1,000万円超の部分については税率を引上げ、3,000万円超では55%に、また、適用税率の刻みを多くしています。
(3)相続時精算課税の適用要件については、①適用対象者に20歳以上の孫を追加、
②贈与者の年齢要件を60歳以上に引下げています。
なお、適用は、相続税は平成23年4月1日以後の相続から、贈与税は平成23年1月1日以後の贈与からです。
H23.1.17
平成23年度税制改正 消費課税編
消費税についての主な改正は、「免税事業者の要件の見直し」と仕入税額控除制度におけるいわゆる「95%ルールの見直し」です。以下、改正内容を確認していきます。
免税事業者の要件の見直し
現行では、前々年(個人)又は前々事業年度(法人)の課税売上高が1,000万円以下の事業者については、その課税期間の課税資産の譲渡等について、消費税を納める義務が免除されています。
しかし、改正案では、原則、①個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高及び②法人のその事業年度の前年事業年(7月以下のものを除く)開始から6月間の課税売上高が1,000万円超えるときは、事業者免税点制度が適用されないとしています。
なお、課税売上高に代えて所得税法に規定する給与等の支払額で判定することもできるとしています。
適用は、その年又はその事業年度が平成24年10月1日以後に開始するものからです。
95%ルールの見直し
現行の仕入控除税額の計算方法は、非課税売上に対応する仕入れについては、原則、仕入税額控除は認められませんが、課税売上割合が95%以上の場合、課税仕入れ等の税額の全額控除が認められていました。
しかし、この95%ルールは、会計検査院、一部の学者や税の専門家から「益税」批判の的となっていたこともあって、今回の改正案では廃止となっています。
※課税売上割合=課税売上(税抜)/課税売上(税抜)+非課税売上
なお、その課税期間の課税売上高が5億円以下の事業者については、現行の95%ルールは存置されています。
適用は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間からです。
この消費税の益税ですが、なにも事業者にだけに生じているわけではありません。国においても益税は生じています。それは、非課税売上に対応する課税仕入れの消費税額です。この金額は、消費課税の仕組みからいえば、本来、事業者に還付すべきものなのです。しかし、国庫に入ってしまっています。これこそが益税です。法律で定めれば、すべてが正義ではありません。会計検査院も税を取ることばかりの提言ではなく、もっと、本質的な議論についても提言をして頂きたいものです
H23.1.14
平成23年度税制改正 法人税編
平成23年度の税制改正における法人課税は、「課税ベースの拡大」と「法人実効税率の引下げ」といった増減税の抱合せが特徴です。何か「帳尻合わせ」で、中途半端の感は歪めません。以下、主な改正項目を確認していきます。
法人実効税率の引下げ
法人税率を現行の30%から25.5%に引下げ、実効税率を5.05%(国税4.18%、法人住民税分0.87%(東京都))引下げています。また、中小法人の年所得金額800万円以下の部分の軽減税率は、引下げ措置が延長され現行18%から15%に、基本税率も22%から19%に引下げられます。適用は、法人の平成23年4月1日以後に開始する事業年度からです。
減価償却費の縮減
定率法の償却率を250%から200%に改正、改定償却率及び保証率についても所要の整備を行うとしています(所得税も同様)。
適用は、平成23年4月1日以後に取得する資産からです。なお、実務上の便宜に配慮し、現行の償却率で定率法にて償却できるなどの経過措置が講じられています。
繰越欠損金の使用制限
改正案では、繰越欠損金の控除限度額を80%に制限しています。なお、中小法人等あっては、現行の控除限度額100%を存置しています。
なお、これに伴い、①繰越欠損金の繰越期間を現行7年から9年に延長(平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額に適用)、②法人税の欠損金額にかかる更正の期間制限を現行7年から9年、請求期間を9年に、また、9年間の記帳保全を期間延長の要件としています。
適用は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度から、また、上記②は平成23年4月1日以後に法定申告期限が到来する法人税からです。
貸倒引当金の縮減
貸倒引当金は、銀行、保険会社その他これらに類する法人及び中小法人等に限定するとし、これ以外の法人については、4年間の激変緩和措置を設けて、現行の損金算入限度額に対する引当を1/4ずつ縮小するとしています。
その他
①雇用促進税制の創設、②仮決算による中間申告の見直し、③一般寄付金の損金算入限度額の縮減などがあります。
H23.1.13
平成23年度税制改正 個人所得課税編
平成23年度の税制改正大綱は、平成22年12月16日に公表されました。改正案は、昨年度改正の「控除から手当へ」に加えて、デフレ脱却と雇用の維持・拡大、格差是正のための所得及び富の再分配機能の回復が主眼です。総じて、高所得者及び遺産取得者に負担を求めているのが特徴です。
それでは、今回、個人所得課税について主な改正項目を確認していきます。
(1)給与所得控除見直し
今まで青天井だった給与所得控除は、収入1,500万超で控除額245万円を限度とし、また、役員等給与(役員としての職務の対価)についても、控除限度額245万円は、収入2,000万超からは逓減、4,000万超で125万円が上限となっています。なお、役員等は、法人税法第2条15号に規定する役員、国会議員及地方議会議員、国家公務員及び地方公務員で一定の職種の者です。
(2)退職所得課税の見直し
役員としての勤続5年以下の当該役員退職手当金については、退職所得控除後の残額の2分の1とする課税措置、いわゆる「2分の1課税」を廃止するとしています。
また、退職所得に係る個人住民税額の10%税額控除を廃止するとしています。
(3)成年扶養控除の見直し
その年の合計所得金額400万円超の人については、年齢23歳以上70歳未満の扶養親族のうち、特定の親族(年齢65歳以上70歳未満の高齢者、障害者、学生等)以外は、扶養控除の対象外となります。なお、その年の合計所得金額400万円超から500万円未満までは控除額38万円を限度として負担調整措置が設けられています。
上記(1)、(3)の改正は、平成24年分以後の所得税及び平成25年分以後の個人住民税から適用されます。また、上記(2)の改正は、所得税は平成24年分以後、個人住民税は平成24年1月1日以後に支払われる退職手当金から適用されます。
(4)その他
①特定支出控除について、その範囲の拡充及び適用要件を緩和、②上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の適用期限を2年延長、③公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、年金以外の所得金額が20万円以下の者について、確定申告不要とする等の改正がなされています。
H23.1.12
所定・法定・実労働時間の違いは何か
労働時間とは
労働時間は「労働者が使用者に労務を提供し、使用者の指揮命令に服している時間」と定義されています。
ご存知のように一口に「労働時間」といってもいくつかの呼び方があります。
「法定労働時間」、「所定労働時間」、「実労働時間」の違いは何でしょうか。
「法定労働時間」とは
労働基準法で定められた労働時間を指します。1週間1日等の一定の期間に労働者を働かせることが出来る上限の時間数(週40時間,1日8時間以内)のことをこう呼んでいます。この「法定労働時間を超えて残業させることは原則としてできませんが、就業規則に業務上の事由があれば労働時間を延長して残業させる事が出来る旨定めてあれば、事業主が「36協定」を締結して届け出た場合には非常の場合を除いて残業を命じる事が出来ます。
「所定労働時間」とは
会社が決めた時間を呼んでいます。会社では始業時刻と終業時刻が決められているのが一般的ですがこの「時刻」を定める事が労働基準法により決められています。会社ではこの決めに基づき各々の会社で働くべき時間とされているものが「所定労働時間」と呼ばれています。
例えば1日7時間30分週休2日とすれば所定労働時間は週37時間30分ですから法定の1日8時間になるまでの30分に割増賃金は発生しません。しかし会社で割増時間とするなら割増賃金をつけてもかまいません。
実労働時間とは
「実労働時間」とは実際に働いた時間という事になります。
従って、所定労働時間に残業時間数を加えた時間になります。
労働時間を整理してみると下記のようになります
法定労働時間 → 労働基準法で定めた労働時間の事
所定労働時間 → 法定労働時間の範囲内で会社が定めた労働時間の事
実労働時間 → 所定労働時間と残業時間をプラスして、実際に労働した時間の事
拘束時間 → 実労働時間と休憩時間をプラスした時間の事
H23.1.11
租税情報交換協定の潮流
租税条約は現在、59の国と地域との間で48条約が締結されています。旧ソ連、旧チェコスロバキアとの条約が継承されている関係で、条約数よりも適用国・地域数の方が多くなっています。
スイスとの租税条約
平成22年5月署名されたスイスとの間の改正租税条約では税に関する情報交換を可能とする内容となっています。
スイスが一貫して銀行機密情報を提供しない方針をとっていたため、日本が締結している租税条約の中で唯一、スイスとの租税条約のみ、税に関する情報交換規定を有しておりませんでした。G20の首脳宣言の中で「銀行機密の時代は終わった。」とされるなど、最近、国際的に税に関する情報交換の重要性が唱えられ、スイスもついに銀行機密情報についての情報交換に応じることを表明せざるを得なくなり、これを受けて、改正されることになったわけです。
バミューダとの租税条約
また、平成22年8月に英領バミューダとの間の租税条約が発効しました。バミューダは外国資本受入れ、外貨獲得の為に、意図的に税金を優遇(無税または極めて低い税率)して、企業や富裕層の資産を誘致する、いわゆるタックスヘイブンの代表的な地域です。租税条約では、通常の場合、税率軽減や免税等の特典を規定するのですが、バミューダには所得に対する租税がありませんので、バミューダとの租税条約の内容は、現在日本が締結している他の租税条約と異なり、内容のほとんどが税に関する情報交換規定となっています。
ケイマンへの情報提供要請
ケイマンは国内法を整備することで、租税条約等の締結に依らない外国税務当局に対する情報提供をすることになり、その情報提供対象国に日本が選定されました。
バミューダ型の租税情報交換規定のみの租税条約は、欧米ではすでに盛んに締結が急がれ、新聞報道によれば、平成21年から平成22年6月までの累計で約300 件にものぼるとされています。
ケイマン型、バミューダ型、スイス型を含め、税に関する透明性を高め、他国との情報交換を積極的に行い、不正資金の排除を行おうとすることは世界的な潮流となりつつあります。
H23.1.7
租税条約の扱いと最近事情
租税条約交渉から発効まで
日本は所得税に対する国際的な二重課税の回避と減免、脱税の防止を目的として多くの国と租税条約を締結していますが、一般的に国家間の租税条約の発効までの手続きは、条約交渉開始、基本合意、署名、国会等での承認、外交上の公文の交換、そしてその交換の日の翌日から30日目の日に発効・公布となります。一般的に、署名から発効まで1年程度の期間を経ることが多いようです。
租税条約の予算並み承認手続き
租税条約の規定は国内法に優先して適用されます。しかし、憲法上、租税条約は「法律」ではなく、「予算」に準じたものと規定されているため、その成立に係る国会の議決の手続きは「法律」よりも軽い扱いを受けています。
つまり、仮に条約案が衆議院は通過したが参議院で「30日以内」に議決等されないような場合、自動的に成立します。「法律」の場合には、衆院通過後参院で「60日以内」に議決されない場合には、参院で否決されたものとみなし、衆議院優越の原則により衆議院で3分の2以上の賛成で再可決するとしているのと比べ、スムーズに手続きが進むよう配慮されています。国内だけでなく、外国との信用問題などがある関係で、予算並みに行政執行機関としての内閣の立場を尊重する位置付けとなっています。
最近の租税条約交渉事情
近年の租税条約の主な改正交渉を見ると資源保有国との租税条約の整備、租税に関する情報交換の枠組構築に力点が置かれている傾向があります。
例えば,ブルネイ、カザフスタン、UAE、クウェート、オーストラリア、サウジアラビアは,豊富な石油・天然ガス、レアメタルその他のエネルギー資源,鉱物資源に恵まれた資源大国であり,また日本企業の出資によってそれらを原料とした製造等も行われております。
香港やシンガポール、スイス、バミューダとの租税条約では新たに情報交換の実施の同意を取り付けたものになっています。五菱会事件というものがあり、闇金融資金を日本から香港、シンガポールの銀行に送金したものにつき、送金先銀行からの情報提供が得られないで捜査の壁に阻まれたという事件がありましたが、こういう事は今後起きないよう祈りたいものです。
H23.1.6
活劇『税務署長の冒険』
数分で読める娯楽短編
国税庁のホームページをたどって行くと「大正12年頃(1923)『税務署長の冒険』」に行き当たります。密造取締りに大活躍する税務署長を描いた宮沢賢治の短編作品を読むことができます。
税務署長のどぶろく密造摘発冒険活劇が内容ですが、署長は村での講演で「どうせやるならなぜもう少し大仕掛けに設備を整へて共同ででもやらないか。すべからく米も電気で研ぐべし、しぼるときには水圧機を使ふべし、乳酸菌を利用し、ピペット、ビーカー、ビュウレット立派な化学の試験器械を使って清潔に上等の酒をつくらないか。もっともその時は税金は出して貰(もら)ひたい。さう云ふふうにやるならばわれわれは実に歓迎する。技師やなんかの世話までして上げてもいゝ。こそこそ半分かうじのまゝの酒を三升つくって罰金を百円とられるよりは大びらでいゝ酒を七斗呑めよ。」などと呼びかけています。
牧歌的な取締りと庶民感覚
酒税は世界各国において、所得税にとってかわられるまでは、税制の中心を占めており、日本においても、自家用酒の製造を全面的に禁止した明治32年以後は、最大税源の酒税収入確保の上からも密造酒対策は重要でした。
『税務署長の冒険』時代は酒税取締りの全盛期であったのでしょうが、当時は、自家製の酒類製造が生活に密着しており、行政側の施策としても、村内の共同出資によって団体を結成し、その代表者の名義によって免許を受けさせ、濁酒を合法的に製造するような態勢へ誘導することにより、世間と折り合いをつけた課税方法を浸透させようとしていたことが伺えます。
当時の民衆感覚は、「①自家用酒は本来の悪事ではない、②小さな密造犯を処分するのは法律の目的ではないはず、③税務官吏の取締は自分の成績を上げるためのもので、罰金のうち何割かは賞与として貰っている、④税務官吏に対する怨恨、⑤密造犯に対する一般的な同情」という具合で、つい争いにつながる傾向がみられたようです。
去るもの日々に疎し
戦後10年くらいまでは、家庭内でのどぶろくの製造は農村では普通のことでしたが、いまや酒類の自家製造は過去のものとなり、逆に『税務署長の冒険』の縁で自己営業場内濁酒製造特区に岩手県遠野市が認められて行政支援を受けています。